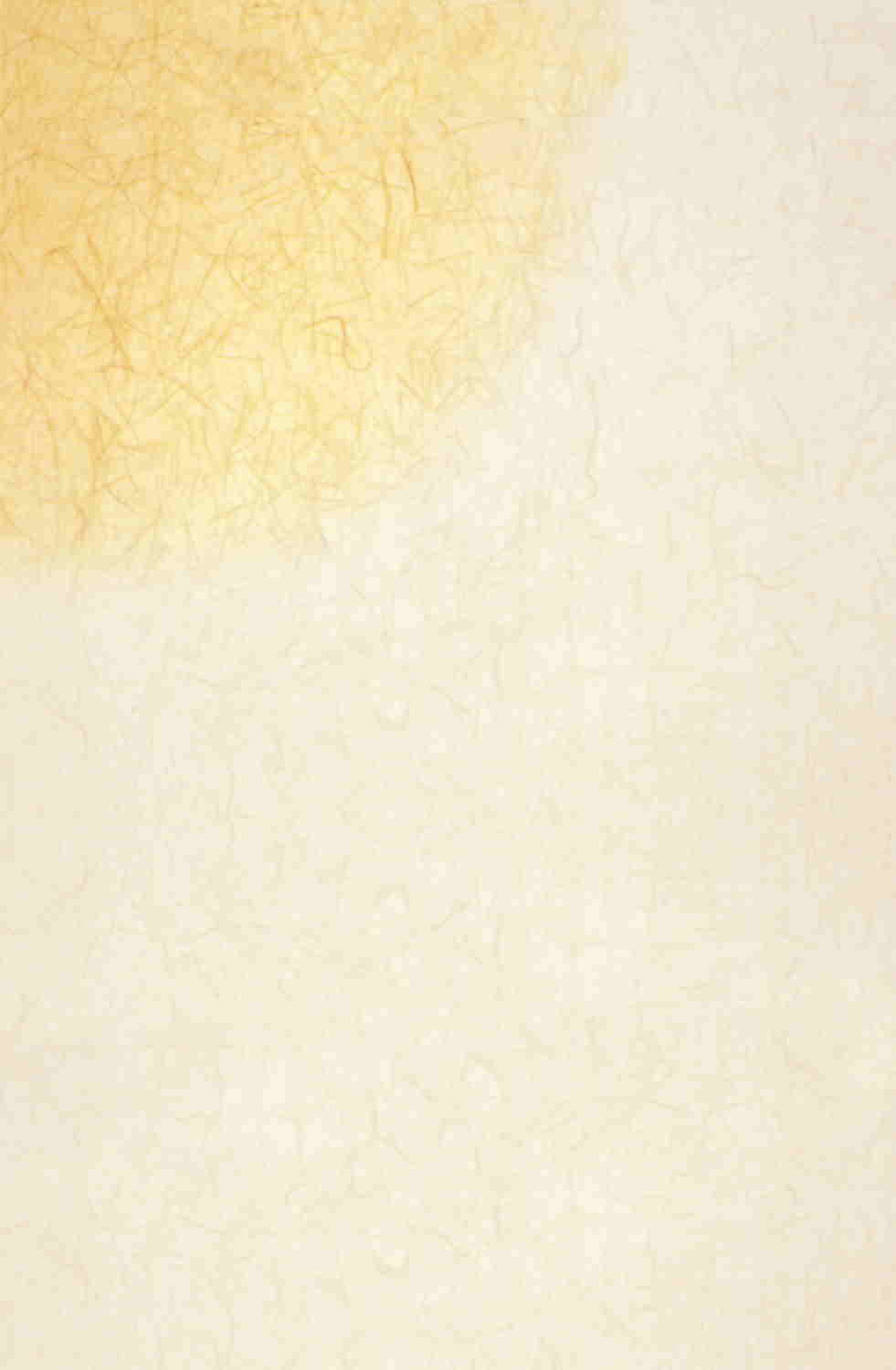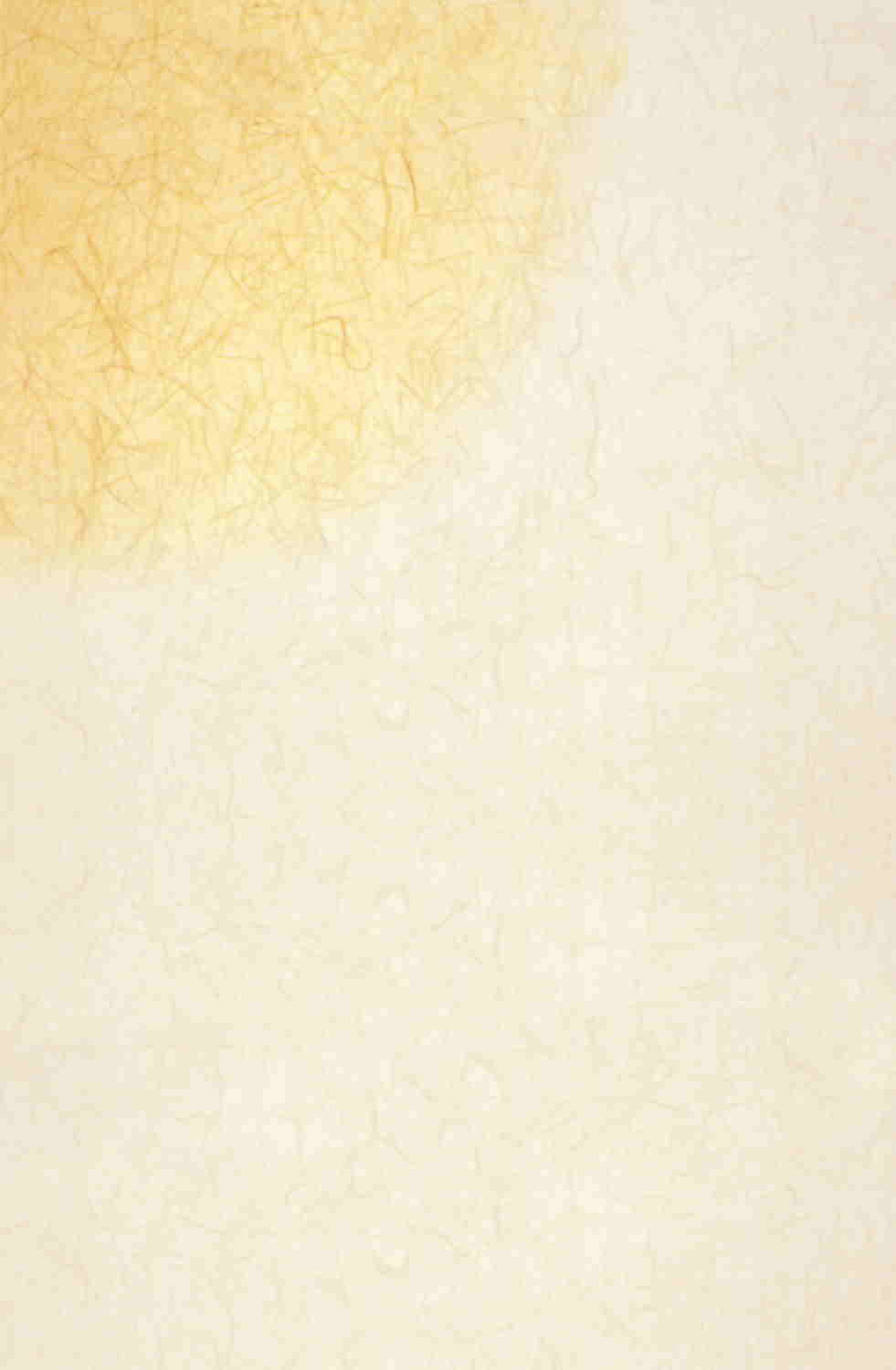
| 市村鉄之助 故郷に帰る |
| 鉄之助が日野を去ったのは、それから十日ほど経ってのことであった。 彦五郎は非常に残念そうであったが、もう止めることはしなかった。またのぶは涙を流して別れを惜んだ。 彦五郎は鉄之助が歳三から渡された二分金でニ百両ほどを預かっていたが、これを横浜の銀行で新紙幣に両替した所、当時流行のガラ金と称するものが混じっていたため減額された。 しかしそれを補ってやり、その上に五十円の餞別を与え、途中まで出入りの者を付添わせてやることにした。 鉄之助の出立の朝は、よく晴れていて、もう庭の桜も満開になっていた。 鉄之助はフトお縫いさんを思い出し、再び会うことのない、この歳三想いの人に故郷へ帰ったら話し残しの隊長のことを手紙で書き送ろうと思った。 力之助と漣一郎が、甲州街道日野大坂の辺りまで送ってくれる。 別れる時に鉄之助は、何故か漣一郎に、「君は勉強が好きだから、医者になり給え」と言った たぶんこの利発な少年の将来に、鉄之助の内心の儚い希望を明かしたのかも知れない。 漣一郎は、今朝は気分が良いので、表庭に縁台を出して、日光浴を楽しんでいた。 彼は、一昨年、待望の東京医科大学(東京帝国大学医学部の前身)に入学することが出来たものの、去年の暮れ頃から微熱がとれず、身体の調子が思わしくないので、正月に帰省してからずっと日野で療養を続けているのであった。 時はすでに、明治十四年一月も半ばである。 不意に頭の上で声がした。 「坊っちゃん、ご機嫌よう」 そこには、田舎では珍しい洋服姿の男が立っていた。 最初は漣一郎には誰だか判らなかったが、」その男は、函館戦争の時、斎藤一諾斎と共に函館を脱走した、元新選組の松本捨助であることに気付いた。 「本宿の捨さんですね」 「はい、そうです。 何ともご無沙汰で申しわけありません。 皆さんご丈夫で・・・・・・。 いや四年前に、御新造さん(のぶ)がお亡くなりになった時には、少し遠方に行っておりましたのでお葬式にも伺いませんで・・・・・・時に、旦那は」 「親父は、いま南多摩郡長をしているので、八王子の方へ行っているので留守ですが、何だか小父さんは、随分ハイカラになったんですね」 「はい。明治になってから私らは、身のおき所もなくなって、ご承知の通り実家は、土方隊長の甥の掟さんに嗣いで貰い、身軽になった私は、日本中ウロつき廻っている始末。 昔の新選組の上がりなんぞは、からっきしいけませんや。 渡り者は格好ぐらいは当世風にしていませんと、馬鹿にされますんで、ハハハハ・・・・・・」 漣一郎は座敷へ招じ入れようとしたが、捨助は急ぎの用事があるらしく、これから八王子の役所の方で彦五郎に会うことにするから直ぐ出かけると言い、また彦五郎に是非伝えておきたいことがあるのだとも言った。 「伝言なら私が伝えますが」 「いや旦那に直接話したいのです。 その方が、あの人も喜ぶと思いますので」 「あの人?」 「はい坊っちゃんも覚えていらっしゃるでしょう、もうかれこれ十年も前のことですが、市村のことを・・・・・・、函館の土方隊長からの使いだと言って来た鉄之助のことですよ」 漣一郎は意外な人の名前が、捨助の口から飛び出したので一応耳を疑った。 鉄之助が、日野を去ってから十年の歳月が経っている。 その頃の腕白坊主漣一郎も、二十二歳の医学生になっていた。 あれからニ、三度便りはあったが、その後、杳として消息はなかった。彦五郎はじめ、一家の者は鉄之助の安否は忘れてはいなかった。とくに、四年前の正月、亡くなった母親おのぶは、歳三の書いた鉄之助を頼むとの、小切れ紙を眺めては、鉄之助のことを心配していた。 |
| 市村鉄之助の消息はいかに ? |
| [小父さん、鉄之助さんに会ったんですか」 「いや、会ったわけではありません。市村君は四年前に死にましたよ・・・・・・。可哀想な奴だが、しかし偉いものだ。立派に土方隊長のお供をしましたよ。一諾斎は坊主だから良いようなものの、俺なんぞは、こうしてぐずぐず生き恥をさらして・・・・・・ それまで立っていた捨助は暗然たる面持で縁台に腰を下ろした。 「実は、私が昨年の暮、美濃の郡上八幡へ、季節外れの無理な異人さんの注文で鯉のぼりの生地を仕入れに行ったとき、そこの一杯飲屋でヒョンな男に出会ったのです。 やはり生地の仲買人みたいな奴でしたが、それが元新選組の市村辰之助ではありませんか。 鉄之助の兄貴ですよ。 お互いにおおぴらに身分なぞは喋りませんが、ヒソヒソ話の末、弟の鉄之助は、結局商売にも馴染めず、「医者の勉強に長崎へ行くのだ」と言って、兄貴のもとを飛び出してしまったそうですが、それがどうしたわけか、あの明治十年の西南戦争に西郷軍に加わり、官軍と戦って、とうとう熊本あたりで戦死してしまったと言うことです。 土方隊長同様に、鉄砲玉を喰らったと言う話で、薄情そうな兄貴も、さすがに涙をこぼしていました。今頃は、あいつは隊長の側で、昔のように隊長自慢の長靴でも磨いていることでしょう」 松本捨助は、八王子を廻り彦五郎に会ってから、横浜へ行くのだと言って帰って行ったが、横浜辺で何か新しい商売でもしているらしかった。漣一郎は、鉄之助の最期を聞き、あの人はやはり、歳三叔父のことが忘れられず、隊長の仇でも討つ気で西郷軍に与し 、官軍に抵抗したのではないかとも思ったが、それだけではなく、あの人の胸底の時勢に乗り切れぬ激しい焦慮による不安が、絶望感になって、ついにそこまで落ち込ませてしまったような気がしてならなかった。 また鉄之助が、兄辰之助に洩らした「医者の勉強に長崎へ行く」と言う一言が妙に漣一郎の胸の奥深く響いた。 それは、十年前の春、鉄之助が日野を去る時、漣一郎に「医者になり給え」と言ったのを今でもはっきりと覚えているからである。 そして漣一郎は、夢多かるべき青春を、幕末維新の動乱の大波に翻弄されて、短い一生を終った鉄之助が、痛ましく、限りなく哀れでならなかった。 だが、その漣一郎も、彼の夢を託していた医科大学の卒業を待たずに、その年明治十四年六月に、ニ十ニ歳の若い命を閉じた。 追記 これは、武州日野宿名主佐藤彦五郎家に、新選組副長、土方歳三の最期の模様をもたらした小姓市村鉄之助の話である。 当時の当主彦五郎は、歳三の姉の夫であると共に、近藤勇の養父周助の高弟で、天然理心流の極意皆伝を許され、歳三の義兄とし、近藤勇の盟友として、新選組の発足より最終まで、最大の新選組後援者として尽くした人である。 その彦五郎の長男源之助こと俊宣の「備忘記」という記録により、この物語を綴ったものであることを諒解せられたい |